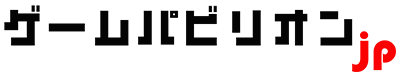インディーゲームのマーケティングに必勝法はない?―海外記事「Which marketing channel provides the best return on investment for small publishers?」を読む
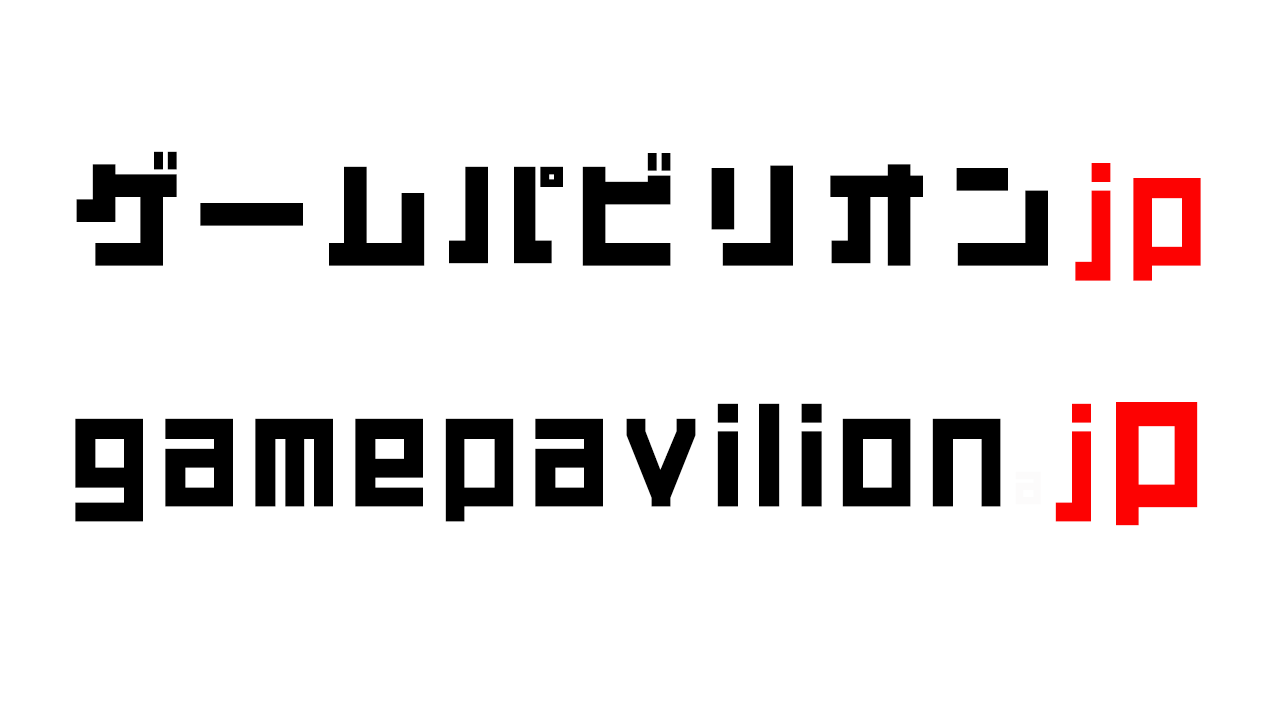
2025年10月31日に公開された海外メディアgameindustry.bizの記事「Which marketing channel provides the best return on investment for small publishers?」は様々な海外パブリッシャーがマーケティングを限られた予算で行っている様子を記しています。これは海外の事例で相当な額の広告費を投じるような事例が多いので、そのまま役立つとは限りませんが有益な指摘も見られると思い紹介したいと思います。
以下は記事の要約です
限られた予算で、小規模ゲームパブリッシャーは広告リターン(ROIA:Return on Advertising Investment)を最大化しなければならない。
ゲームのリリース時期は依然として最も重要な宣伝のタイミングでり、特にSteamでのリリースにとっては決定的だ。
Future Friends Gamesの創設者トーマス・ライゼンエッガーはこう述べている。
「もしプレイヤーがゲームをすぐに気に入らないと、Steamのアルゴリズムはあなたの作品を埋もれさせてしまう」
『Planet Centauri』はSteamの不具合により、ウィッシュリストに登録していた13万人以上のユーザーに1.0リリースの通知が届かなかった。その結果は発売から5日間の購入はわずか581人にとどまった。インディー作品にとって、ローンチ時の注目不足は壊滅的な打撃になる。
では、どのようなマーケティングチャネルを使って注目を集められるだろうか?
有料ソーシャル広告(Paid Social)
Fellow Traveller社のマーケティング責任者マーラ・フィッツシモンズは、『Wander Stars』のほか『Paradise Killer』や『Citizen Sleeper』を手がけている。
彼女はゲームの周囲にコミュニティを育てることがROIA(広告投資利益率)最大化の鍵と考えており、広告展開ではコミュニティ志向のソーシャルプラットフォームに重点を置いている。
「TikTokとRedditに注力しています。プレイヤーと直接つながり、ゲームに関する会話を生み出すチャンスを与えてくれます――もちろん、それぞれ異なる形でです」
「プレイヤーたちがすでに好きなゲームについて語り合っているので、“適切なプレイヤー層”を狙いやすく、新タイトルを彼らの視野に入れる良い方法だと感じています」
ただ、成功が保証されるわけではない。
『Flocking Hell』の開発者はReddit上に、低いコンバージョン率やプラットフォームの手数料などがROIAを圧迫し、結果的に「小規模パブリッシャーにとって有料広告は割に合わない」と投稿している。
これについて、フィッツシモンズはマーケティング予算を2つに分割すべきと提案している。
「認知チャネル(awareness channels)」――ゲームの存在を知ってもらうためのもの。
「信頼性が高く、権威のある情報源」――コンバージョン(購入・参加)率を高めるためのものである。
「私たちの経験では、“マルチチャンネル戦略”が最も効果的だとわかりました。」
「プレイヤーはTikTokのような“認知チャネル”でゲームを目にし、フォローしているジャーナリストやクリエイターがそのゲームについて言及するのを見かけると、私たちのコミュニティを訪れて他のプレイヤーの声を聞こうとする傾向が高まります。」
ホラーゲームのパブリッシャー DreadXP のディレクター、ハンター・ボンドもこの意見に同意するが、ソーシャルプラットフォームはアルゴリズム(や所有者)を絶えず変更し広告戦略を妨げているとも指摘している。
「今のインディーは難しい。時間をかけた努力に対して、どこで最も良いROI(投資対効果)が得られるのか―“正解”がひとつも存在しない」
No More Robots の創設者マイク・ローズは、10月7日に発売された『Little Rocket Lab』のリリースが同社にとって初めて有料広告を投じたローンチだったと語る。それはリリース初期という最も重要な時期に確実に注目を集めるためだった。
「総額でおよそ5万ドルを使いました。まず“Next Fest”のタイミングで広告を打ち、リリース直前の数週間でさらに広告を出しました。ローンチ当日に“誰もがこのゲームを目にするように”配信したんです」
彼は、直接的に売上を伸ばすのではなく認知を高めるために広告を使った。
「広告を見た人がすぐ“購入ボタン”をクリックするとは思いません。ただ、“同じものを3回見ると興味を持つ”という古い黄金則がありますよね。私はローンチ前の数週間で『Little Rocket Lab』を広告で“あちこちで見かける存在”にできたと思っています。だから人々がSteamでゲームを見たときに“よく見かけたゲームだ。しかも25%オフで評価も高い”と感じるようにできました」
ローズはこう語り、『Little Rocket Lab』のローンチは成功だったと結論づけている。
ライブイベントとコミュニティ
ボンドは『Heartworm』や『The Mortuary Assistant』などホラー系パブリッシャー DreadXPのディレクターで、広告は「自然発生的なマーケティング活動(オーガニック・キャンペーン)」を補完する場合にのみ使うと語る。広告を“後押し”として使うという立場だ。
ボンドによるとDreadXPではマーケティング予算の一部をPAXのようなイベントでプレイヤーやメディアと直接会うために使っているという。
「口コミ(word of mouth)は昔から最も効果的なマーケティング手段です。これは“お金で買うことができない唯一の広告形態”です。自分たちが約束したものを本当に提供するから、誰かが“このゲームを試してみて”と勧めてくれる。有料チャネルやメディア露出だけに頼るマーケティングは、どこか欠けています。私は“実際にゲームを買ってくれる人々に直接届く努力”こそが重要だと思っています」
一方、No More Robots のマイク・ローズは、ライブイベントにはゲームを効果的に宣伝するための十分なインフラが整っていないと考えている。代わりに、彼は『Little Rocket Lab』の成功を受けてコミュニティ主催のデジタルイベントへの参加を強く薦めている。
「2024年末、“Wholesome Snack”というオンラインショーケースで初めてこのゲームを披露しました。そして約8,000件ものウィッシュリスト登録を獲得できました。もしショーケースに参加できるチャンスがあるならそれは良いアイデアです。“Wholesome Showcase”は完璧な舞台でした」
ストリーミングでの成功
過去10年間、ストリーマーや動画クリエイターは他のメディアに取って代わる存在となった。多くのパブリッシャーは信頼できる配信者とつながることを望んでいる。
この戦略には2つの利点がある。
1つ目は、配信者のオーディエンス規模に応じて費用が抑えられる。
2つ目は、先述のフィッツシモンズが語った「認知(Awareness)とコミュニティ形成のちょうど中間に位置するマーケティング手法」を実現できる。
ゲーム業界専門のエージェンシー Yrs Truly が最近発表した「Gaming Content Creator Report」によると65.9%のクリエイターがインディー向けの別料金を設定しており、配信者の視聴者層とゲームのターゲット層が一致している場合にこの傾向が強いという。
これは、小規模パブリッシャーにとってスポンサー付き配信やコラボ企画でROIAを最大化するチャンスとなる。さらに重要なのは、これらが「認知チャネル」上での露出機会を生み出すという点でもある。
フィッツシモンズは次のように語っている。
「最も良い結果が出るのは、配信者自身が本当にゲームを楽しんでいてそのコミュニティと自然にマッチしているときです。私たちはスポンサーシップを“ポジティブな評価を買うため”の手段とは考えていません。それより“プレイヤーがすでに信頼している声”を通じて、新しいゲームを発見する手段と考えています。適切な配信者と適切な視聴者の組み合わせは非常に効果的なマーケティングツールです」
しかし配信によるPRは、無料ではない。
以前は「配信者にお金を払ってゲームを紹介してもらう」という関係に反対していたNo More Robotsのマイク・ローズも、今ではそれを避けられないと受け入れている。
「いまやYouTuberは報酬を求めるようになっています。こちらも“そのルールに従うしかない”。そうでないと、YouTubeで自分たちのゲームを見ることはできないでしょう」
彼は現在、インフルエンサー費をすべてのゲームの予算に組み込むようにしている。
ローズはこの支出はディスプレイ広告と同様、明確な数値根拠を持って正当化するのが難しいと認めている。ボンドも次のように指摘する。
「インフルエンサーやスポンサー配信は、マーケティング支出の中でも最も曖昧です。データドリブンな観点から見ても結果予測は不可能に近く、費用対効果を直接測定するのも難しい。投入した金額に本当に価値があったのかを事前に判断することはほぼ不可能です」
小規模パブリッシャーであっても多様なプラットフォームで有料広告の配信は可能だが、成功が保証されるわけではなく“魔法の弾丸”のような必勝法は存在しない。
広告は、コミュニティ中心の有機的なマーケティング活動と組み合わせてこそ効果を発揮する。プレイヤーとの直接的なつながりを通じてゲームへの関心を育てリリース直前のタイミングで広告を「増幅装置」として活用するのが理想的だ。
ローズは最後にこう語る。
「広告は“人々の脳の片隅にあなたのゲームを残すもの”です。コミュニティやショーケース、口コミなどを整えておけば、ローンチのタイミングで効果がきっと現れます」
読む方がディベロッパーかパブリッシャーかでも考えは異なるかもしれませんし、私のような展示会主催者の考えも読者の皆さんと異なるかもしれません。ローンチまでのPRが重要だという点は私も同意するところで、海外の記事らしく最初からメディアをあまりアテにしていない(海外のゲームメディアはAAAが中心になり、インディゲームはあまり掲載されない。あるいはヒットしてから掲載される)点もポイントだと思います。インディゲームを取り上げるゲームメディアがある分、できることが多いのかもしれません。
私の考えでは、展示会の来場者とは”出展タイトルに関心がある方の総和”です。Aというタイトルに関心がある方が展示会に来場し、BやCにも触れてその良さを理解する。その体験こそが展示会だと考えています。ストリーマの配信などに比べると範囲は狭いのですが熱心なファンを作る場として機能していると思いますし、ディベロッパーであれば目の前でプレイしてもらうことで自分の伝えたいことが伝わっているのかを確認する機会にもなります。
そう考えると、どんどん出展したほうがいいように思えますがそう簡単でもありません。
展示会に出展するタイトルに何らかのアップデートや目新しさがあった方が注目は高まります。これは会場を見ていると感じますが新作を出展されるスペースはよく賑わっていて、すでにリリースした作品でもアップデートなどがあれば既存のファン層が立ち寄って賑わっているように思います。前と同じ内容のままでは熱心な固定ファンも他の出展タイトルに行ってしまう傾向があるようです。(ただ、初めて知った新規のファンも展示会では獲得できるので同じ内容の出展でもまったく効果がないわけではないようです)
インディーゲーム開発の難しいところですが展示会に出展するとその期間は開発が止まることが多く(展示会を広報や営業チームに任せることはあまりないと思います)プレイヤーが期待している作品の完成やクオリティアップと相反してしまいます。もちろん、プレイヤーに知ってもらうことは重要なのですがこのバランスが難しいのだと感じます。
展示会の主催者としては、出展者の皆さんのゲームができるだけ多くの人に知ってもらい売れてほしいと思っていますのでSteamにページを作ったり当日配信をしたり、今回からはトレイラーを公式Youtubeチャンネルで配信するゲームパビリオンjp LIVEを行おうと思っています。
“魔法の弾丸”のような必勝法は存在しない中で、何をするのか難しいところです。